「売れない…。」「使えない…。」「管理できない…。」
そのような”負”動産を手放したいとき、
その土地を国に引き渡すことができる相続土地国庫帰属制度という制度があります。
本記事では制度の概要について詳しく解説します。
相続時の土地の処分方法
そもそも相続した土地にはどのような処分方法があるのでしょうか。
①自分で活用する
相続して取得した土地は自分で活用することができます。
住みやすい場所なら自分で家を建てて住んだり、
住宅街の中なのであれば駐車場として人に貸したりすることが考えられます。
②売却する
土地の管理が大変な人は売却することもおすすめです。
土地は持っていると固定資産税などの費用がかかります。
近くの不動産屋さんに相談して売却し、お金に変えてしまうのもおすすめです。
③相続放棄する
相続した土地によっては上記のような活用が難しい土地もあるかと思います。
その場合、相続放棄という手も考えられます。
相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内に申し立てることが可能です。
但し、相続放棄をしてしまうと土地だけでなく預貯金などの資産や権利も全て放棄することになるので注意が必要です。
関連記事:(相続放棄と限定承認の違い 徹底解説)
④相続土地国庫帰属制度
活用の難しい土地について、国が引き取ってくれる制度があります。
道路に接していない土地、山林、原野など販売しても買い手がつかないような土地におすすめの制度です。
相続土地国庫帰属制度の概要
相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈で受け継いだ土地を条件を満たせば国に引き渡して手放せる制度です。この制度は土地が放置され将来的に所有者不明の土地の発生を防ぐことを目的に令和5年4月27日に施行されました。
本制度が施行されたことにより条件に当てはまれば土地を手放し、ほかの財産は手元に残すことが可能となったのです。但し、対象とならない土地もあるので注意が必要です。
相続土地国庫帰属制度の対象とならない土地
【申請をすることができないケース(却下事由)】
A 建物がある土地
B 担保権や使用収益権が設定されている土地
C 他人の利用が予定されている土地
D 土壌汚染されている土地
E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
【承認を受けることができないケース(不承認事由)】
A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
(引用: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html#mokuji4)
いずれも相続または遺贈にて取得した土地が対象です。
売買等で取得した土地は対象外なのでご注意ください。
また、審査申請手数料と引き取り確定時に管理費用の一部を納める必要があります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
相続土地国庫帰属制度は、“相続したらずっと持ち続けるしかない”と
思われていた土地に新しい選択肢を与えてくれる制度です。
処分に困っている土地がある方は一度法務局に相談してみてもいいかもしれません。
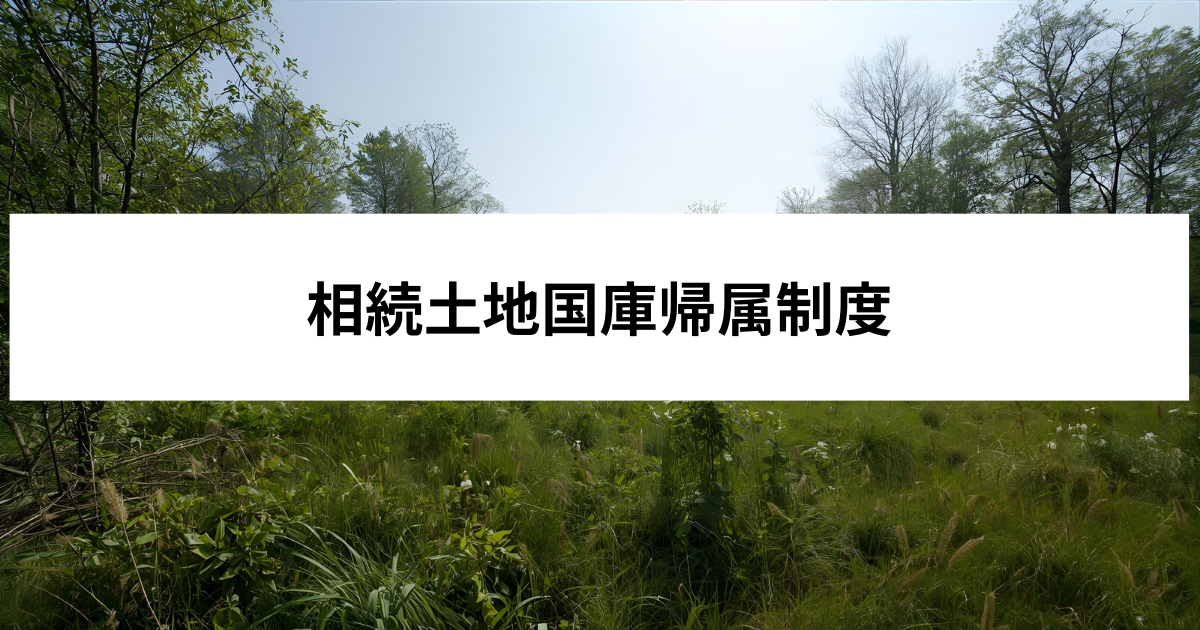
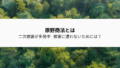

コメント